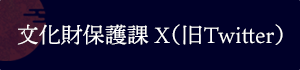本文
関連文化財群(12) 安穏な生活への願いと祈り
概要
市内各地で行われる祭りや年中行事、信仰とそれらに関する歴史文化資源からなり、市内全域に分布します。
主な構成要素
地福のトイトイ
1月14日夜、子どもたちが集落の家々を1軒ずつまわり、持参した藁馬と供物とを交換する。家内安全や無病息災、五穀豊穣等を祈願する小正月の訪問者の行事である。

陶の腰輪踊
8月28日に、陶の八雲神社(荒神社)の神事として境内で舞われる踊り。八雲神社に所蔵されている「当屋名寄帳」によると、およそ400年以上前から、念仏踊りとして行われていたことが分かる。

須賀社の厄神舞
厄神舞は毎年須賀社の秋季例祭日(旧暦10月初めの子と丑の日)の初日の夜8時ごろから行われる。チャンチキ舞に属しており、厄除けの願舞で氏子や信者の立願いによって舞うもので、平安時代から続けられているという。

生雲八幡宮奴道中
萩の金谷天神から伝承したもので、毎年10月の第一日曜日、生雲八幡宮大祭のお旅所への道中往復に奴道中が行われる。
秋穂八十八ヶ所霊場巡り
秋穂の真善坊の住職性海が四国八十八ヶ所を何度も巡拝し、天明3年(1783)に秋穂、秋穂二島、名田島に勧請したもの。

平川の大スギ
スギはスギ科の常緑針葉高木。平川の大スギは、山口市吉田、高倉山の平清水八幡宮社有地にある巨木。