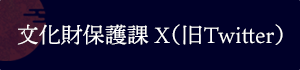本文
須賀社の厄神舞
すがしゃ の やくじんまい

文化財指定等状況
市指定
指定区分
無形民俗文化財
指定年月日
昭和48年7月20日
種別
無形民俗文化財
時代(大分類)
古代
時代(小分類)
平安
地域
阿東(嘉年)
所在地
山口市阿東嘉年下
概要
説明
厄神舞は毎年須賀社の秋季例祭日(旧暦10月初めの子(ね)と丑(うし)の日)の初日の夜8時ごろから行われる。
この舞の発祥は古く、平安時代にさかのぼる。長元6年(1033)の夏、この地方は酷暑の日が2ヶ月以上も続き、稲は枯死してしまった。その上、悪疫が流行して里人は度重なる苦しみに喘いだ。ある日、東の空が俄かに曇り、雷鳴が轟き、稲妻が走って大雨となった。激しい雨足を呆然と眺めていた勘蔵という老人は、西方の空にピカリと光って山上に降りてくる物を見かけた。もしかしたら、神の救いの前兆かと里人達と相談し、恐る恐る山上に登ってみると、そこに二振の小太刀があった。里人達は小太刀をご神体とし、「素盞鳴命(すさのうのみこと)」を祭神として社を建立し、神楽舞を奉納した。すると、流行していた悪疫もやみ、明るい村に蘇った。以来、毎年やむことなく舞が続けられている。
この舞の発祥は古く、平安時代にさかのぼる。長元6年(1033)の夏、この地方は酷暑の日が2ヶ月以上も続き、稲は枯死してしまった。その上、悪疫が流行して里人は度重なる苦しみに喘いだ。ある日、東の空が俄かに曇り、雷鳴が轟き、稲妻が走って大雨となった。激しい雨足を呆然と眺めていた勘蔵という老人は、西方の空にピカリと光って山上に降りてくる物を見かけた。もしかしたら、神の救いの前兆かと里人達と相談し、恐る恐る山上に登ってみると、そこに二振の小太刀があった。里人達は小太刀をご神体とし、「素盞鳴命(すさのうのみこと)」を祭神として社を建立し、神楽舞を奉納した。すると、流行していた悪疫もやみ、明るい村に蘇った。以来、毎年やむことなく舞が続けられている。
関連文化財群
安穏な生活への願いと祈り
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>