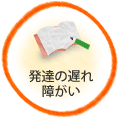利用者負担額(保育料)について
利用者負担額(保育料)の算定方法やお支払い方法については、以下のとおりです。
副食費(給食のおかず代)については、原則みなさまにご負担いただきますが、一定の要件を満たす場合に徴収免除措置があります。副食費の徴収免除判定方法やお支払い方法については、副食費についてをご確認ください。
利用者負担額の算定方法
利用者負担額は、父母の市民税額の合計を、次の『利用者負担額表』に当てはめて決定します。
ただし、父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母のうち最多収入者を家計の主催者とみなし、その主催者の市民税額も合算して利用者負担額の階層を決定します。(詳細は下記)
令和7年度 利用者負担額表(阿東地区の園のみ) [PDFファイル/107KB]
算定基準となる税年度は次の表のとおりです。
毎年9月には、算定基準となる税年度が切り替わるため、すべての児童を対象に再算定を行います。
| 年度 | 月 | 算定に利用する市町村民税額の年度 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 4月~8月分利用者負担額 | 令和6年度市町村民税額(令和5年中の収入に基づくもの) |
| 9月~3月分利用者負担額 | 令和7年度市町村民税額(令和6年中の収入に基づくもの) | |
| 令和8年度 | 4月~8月分利用者負担額 | 令和7年度市町村民税額(令和6年中の収入に基づくもの) |
| 9月~3月分利用者負担額 | 令和8年度市町村民税額(令和7年中の収入に基づくもの) |
※住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)、配当控除、寄付金控除などの税額控除は、利用者負担額の決定に使用する市民税額には適用されません。
※税源移譲が行われた指定都市で市民税が課税されている場合、税源移譲前の旧税率で計算した市民税額を使用します。
※確定申告などで市民税額に変更があった場合や、家族構成に変更があった場合(婚姻・離婚、事実婚の開始・解消、祖父母との同居・別居など)は、利用者負担額が変更になる可能性がありますので、すみやかに山口市保育幼稚園課まで届け出てください。
ひとり親世帯・障がい者と同居されている世帯の軽減について
市民税所得割額77,200円未満に該当する世帯で、ひとり親世帯、または、次の《》のいずれかの手帳等の交付を受けている方と同居(園児本人も含む)している場合は、各手帳等の提出された翌月分から利用者負担額を軽減します。該当世帯で未提出の場合は、手帳等の提出をお願いします。
《身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特別児童扶養手当の支給証書、国民年金の障がい基礎年金証書》
父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる世帯について
父母の合計収入が103万円以下で、同居している祖父母等がいる場合は、祖父母等のうち最多収入者を家計の主宰者とみなし、その主宰者の市民税額も合算して利用者負担額の階層を決定します。この場合の祖父母等は、直系尊属または養子縁組によって生じた親子をさします。
また、その決定した階層に応じて利用者負担額が軽減される場合があります。
| 階層 | 軽減割合 |
| C1~D2の世帯 | 100%軽減 |
| D3~D6の世帯 | 50%軽減 |
| D7~D13の世帯 | 軽減なし |
第2子以降の利用者負担額(保育料)の無償化について
令和6年9月以降から第2子以降の3歳未満児について、世帯の所得やきょうだいの年齢、保育所等の同時入所に関わらず、保護者が監護し生計が同一のお子さんのうち第何子であるかを決定した上で、利用者負担額(保育料)が無料となります。
【無償化の対象外】
・預かり保育事業
・保育所・認定こども園等で行う一時預かり事業
・病児保育事業
・ファミリー・サポート・センター事業
認可保育施設を利用している場合
【対象施設】
・保育所
・認定こども園(保育園部分)
・地域型保育事業所
・へき地保育所
【手続き】
・原則、手続きは不要です。
※18歳以上や別居しているお子さんがいる場合(就学、療養等)は、お子さんの扶養の確認のため、生計を同一にしている旨の申立書や確認できる書類(健康保険証等)の提出が必要となります。
認可外保育施設を利用している場合
市町村民税課税世帯で保育を必要とする第2子以降のお子さん(0~2歳児クラス)が、施設等を利用する場合の利用者負担額(保育料)を無償化(月額上限あり)します。
※市町村民税の非課税世帯は手続きが異なります。
【対象施設】
・認可外保育施設
・企業主導型保育施設
※対象施設は、県に届出を行い証明書を交付されている施設に限ります。詳しくは県のホームページ<外部リンク>をご確認ください。
【無償化の内容】
認可外保育施設:月額上限42,000円
企業主導型保育施設:0歳児 月額上限37,100円
1~2歳児 月額上限37,000円
※施設に支払った利用者負担額(保育料)または月額上限額、いずれか低い額を給付します。
【認定手続き】
・多子世帯(無償化)の給付を受けるためには、事前に山口市から「多子世帯利用給付認定」を受ける必要があります。保育幼稚園課または各総合支所へ必要書類をご提出ください。
※窓口では個人番号(マイナンバー)の確認も行いますので、同居ご家族全員の個人番号(マイナンバー)がわかるものと窓口に来られる方の本人確認書類もお持ちください。
※利用施設によっては、必要書類をとりまとめている場合もございますので、各施設にご確認をお願いします。
〈必要書類〉
・多子世帯利用給付認定申請書(様式第1号)【両面印刷】[PDFファイル/415KB]
・保育の必要性を証明する書類(父母どちらも必要)
※該当者のみ
・利用者負担額等別居監護申立書 [PDFファイル/419KB](18歳以上や就学等で別居しているお子さんがいる場合は、扶養の確認のため健康保険証写し等の確認書類とあわせてご提出ください。)
【給付請求手続き】
・給付は償還払いで行います。(保護者が施設に支払った保育料を、後日必要な手続きをすることで、上限額の範囲でお支払いします。)
・保育幼稚園課または各総合支所へ必要書類をご提出ください。
〈必要書類〉
・多子世帯利用費請求書(様式第5号)【両面印刷】 [PDFファイル/494KB]・・・認定保護者様にて記入してください。
・領収書兼提供証明書 [PDFファイル/58KB]・・・利用施設から交付を受けてください。
〈請求書の提出期限と支給月〉
| 利用月 | 請求書提出締切 | 振込日の目安 |
|---|---|---|
|
令和7年4・5・6月 |
令和7年7月11日(金曜日) | 令和7年7月31日(木曜日) |
| 令和7年7・8・9月 | 令和7年10月10日(金曜日) | 令和7年10月31日(金曜日) |
| 令和7年10・11・12月 | 令和8年1月9日(金曜日) | 令和8年1月30日(金曜日) |
| 令和8年1・2・3月 | 令和8年4月10日(金曜日) |
令和8年5月13日(水曜日) |
※注意 令和8年4月10日(金曜日)の締切日までに請求がない場合は、令和7年度分のお支払いはできません。
利用者負担額のお支払いについて
認定こども園・地域型保育施設・山口市外の公立施設を利用の場合
利用施設にお支払いいただくようになりますので、詳しくは利用施設に直接お問い合わせください。
上記以外の施設を利用の場合
山口市にお支払いいただくようになります。お支払いには、口座振替をご利用ください。
口座振替のお手続きに必要な「口座振替依頼書」は、利用施設(山口市内の施設に限る)または山口市保育幼稚園課(各総合支所総合サービス課を含む)にてお渡ししております。
※残高不足により口座振替ができなかった場合は、翌月中旬に「利用施設へ現金納付」もしくは「納付書払い」でお支払いいただきます。
※滞納されると、利用者負担額とは別に、督促手数料(1件につき100円)と延滞金をいただきます。
【令和7年度の納期限一覧】
口座振替は、納期限が引き落とし日です。
納期限は毎月月末(ただし、12月は12月26日)ですが、土日と重なる場合は翌営業日となります。
| 期別 | 納期限 | 期別 | 納期限 |
|---|---|---|---|
| 令和7年4月分 | 令和7年4月30日(水曜日) | 令和7年10月分 | 令和7年10月31日(金曜日) |
| 令和7年5月分 | 令和7年6月2日(月曜日) | 令和7年11月分 | 令和7年12月1日(月曜日) |
| 令和7年6月分 | 令和7年6月30日(月曜日) | 令和7年12月分 | 令和7年12月26日(金曜日) |
| 令和7年7月分 | 令和7年7月31日(木曜日) | 令和8年1月分 | 令和8年2月2日(月曜日) |
| 令和7年8月分 | 令和7年9月1日(月曜日) | 令和8年2月分 | 令和8年3月2日(月曜日) |
| 令和7年9月分 | 令和7年9月30日(火曜日) | 令和8年3月分 | 令和8年3月31日(火曜日) |