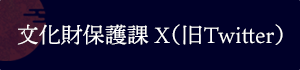本文
関連文化財群(9) 古代山陽道沿線に展開した工業地帯
概要
古代山陽道沿いに展開した工業生産に関わる遺跡、地名を中心とする歴史文化資源からなり、陶、鋳銭司地域に分布します。
主な構成要素
陶陶窯跡
陶の地名のとおり、ここで産出する良質の粘土を原料として、須恵器を製作していた。昭和11年(1936)に発見され、内部から多数の陶器片が出土した。この種の窯跡は付近一帯に広く分布しており、古くから須恵器の産地として有名である。

百谷窯跡
小郡下郷の石槌山の標高75mの急斜面に築かれた須恵器窯跡。窯の形態と出土した土器類から平安時代以降に造られたと推定されている。全体の規模は古代の登窯としてはやや小さい。

周防鋳銭司跡
鋳銭司は古代の銭貨鋳造所。周防鋳銭司は全国に置かれた鋳銭司のうちで最も長期間貨幣の鋳造が行われ、平安時代の820年代から950年にかけては唯一の銭貨鋳造所であった。

周防鋳銭司跡出土品
昭和40年度(1965)に行われた周防鋳銭司跡第1次調査で出土した遺物である。鞴羽口、坩堝、印影粘土板等からなる。

司家遺跡
鋳銭司の政務をつかさどった官庁を司家(じけ)という。この地はその跡と伝えられている。

鋳銭司古図
本絵馬は、明治時代前半に描かれたとされ、陶と鋳銭司地区に広がる鋳銭司関連の地名・旧跡を鳥瞰的に示し、当時の海岸線も表している。