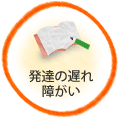令和7年度保育の必要性の認定
保育施設の利用を希望する場合には、下記の教育・保育給付認定を受けていただく必要があります。教育・保育給付認定の申請は入園の申し込みと同時に行うことができます。
申請後、認定された場合、「教育・保育給付認定決定通知書」を交付します。
※認定申請の結果の通知は申請から30日以内が原則とされていますが、4月申し込みについては申請が混み合うことから、結果の通知は利用調整結果の通知と合わせて行います。
教育・保育給付認定区分
2号認定・・・子どもが満3歳以上で、保育の必要な理由に該当する場合
3号認定・・・子どもが満3歳未満で、保育の必要な理由に該当する場合
※「1号認定」は、保育の必要な理由に該当せず、幼稚園や認定こども園での教育を受ける場合の認定です。ただし、阿東地域の保育園については、満3歳以上の子どもに限り、1号認定でも入園できます。
以下、2号認定・3号認定をまとめて「保育認定」といいます。
保育の必要な理由
保育認定を受けられるのは、保護者のいずれもが次の理由に該当する場合です。
1.就労
一月あたり64時間以上労働している
2.妊娠・出産
母親が出産の前後である(産前産後8週に限る)
※妊娠・出産で、出産予定日(出産日)の産前産後8週の期間については、就労している場合でも、原則妊娠・出産での認定になります。
※妊娠・出産の理由で入園された場合は、産後8週の月末で必ず退園となります。
3.疾病・障がい
病気・ケガをしている、または心身に障がいがある
4.親族の介護・看護
常時(一月あたり64時間以上)、病気・ケガや障がいのある方の介護・看護をしている
5.災害復旧
震災、風水害、火災その他の災害の復旧にあたっている
6.求職活動中
求職活動(起業の準備を含む)を継続的に行っている
7.就学・職業訓練
一月あたり64時間以上、教育施設に就学している、または職業訓練を受けている
8.その他
上記に類する理由で家庭での保育が困難とみなされる場合
※保育認定されても、施設の定員に余裕がない場合など、施設を利用できない場合があります。
保育認定の有効期間および入園期間
入園は原則毎月1日からとなります。
入園期間は保育認定の有効期間と原則同じです。
保育認定の有効期間
- 2号認定・・・原則、小学校就学前まで
- 3号認定・・・原則、3歳の誕生日の前々日まで
(引き続き保育が必要な理由に該当していれば、3歳の誕生日の前日から自動的に2号認定に切り替わります。)
※ただし、上記期間内に「保育の必要な理由」を満たさなくなった場合は保育認定が取り消され、保育施設の利用ができなくなります。
また、以下の場合には認定の有効期間および施設の入園期間が制限されます。
- 出産
産後8週の属する月の月末まで - 求職活動中
2か月間(この間に一月64時間以上の就労証明書を提出し、再度保育認定を受ければ継続利用可) - 就学
卒業予定日または修了予定日が属する月の末日まで
(ただし卒業後2か月以内に一月64時間以上の就労証明書を提出し、再度保育認定を受ければ継続利用可)
保育必要量(保育施設を利用できる時間)
保育認定を行う際、保育必要量の認定も行います。
保育の必要量は「保育標準時間」と「保育短時間」の区分があり、一日あたりの利用できる時間や利用者負担額が異なります。
(1)保育標準時間・・・最長11時間利用(フルタイム就労を想定)
(2)保育短時間 ・・・最長8時間利用(パートタイム就労を想定)
保育必要量は、保育を必要とする理由や就労時間等によって認定します。
- 保護者が就労している/就学中である/親族の介護・看護している
月120時間以上 ・・・ 標準時間・短時間どちらでも選択可
月64時間 から 120時間未満 ・・・ 原則短時間 ※標準時間を希望できる場合もあります。詳しくはご相談ください。 - 保護者の心身に病気や障がいがある
・・・ 原則短時間(※ただし、8時間以上の保育を常時必要とする医師の診断書があれば、標準時間認定する場合もある) - 母親が妊娠・出産前後である/保護者が震災等の災害の復旧にあたっている
・・・ 標準時間 - 保護者が求職活動中である/育児休業取得時に既に保育を利用している子どもがおり、育児休業中も利用を継続する場合
・・・ 短時間
※父母のどちらかの要件が保育短時間であれば、「保育短時間」での認定となります。
詳しい保育時間の仕組みについては、下記関連書類「保育時間の仕組み」(PDF)をご覧ください。