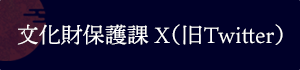本文
梵鐘 [萬福寺]
ぼんしょう

文化財指定等状況
市指定
指定区分
有形文化財
指定年月日
昭和51年12月21日
種別
有形文化財(美術工芸品)
美術工芸品の分類
工芸品
時代(大分類)
近世
時代(小分類)
安土桃山
地域
嘉川
所在地
山口市嘉川2091番地 萬福寺
概要
説明
竜頭は太く堂々としており、撞座は八葉の蓮華座であるが、中房が複雑で豊かであり、池の間の4区に銘文が彫られている。
銘文によると、天正4年(1576)に久芳賢直が長門府中の鋳工安尾春種に鋳造させて、嘉川八幡宮に寄進したものとわかる。久芳賢直は北条時政の子孫で、芸州久芳村を領して久芳氏を称し、大内氏に仕えていたが大内氏滅亡後は毛利元就に仕え、賀川地方(山口市嘉川)の領主となった。安尾春種は、長州府中(下関市長府町)の南金屋の鋳物師である。安尾氏は、その系図によると鎌倉時代から府中で鋳物師を世襲し近世に至っている。
萬福寺は嘉川八幡宮の社坊であったが、明治の神仏分離に際し、この梵鐘は嘉川八幡宮から萬福寺に移された。
銘文によると、天正4年(1576)に久芳賢直が長門府中の鋳工安尾春種に鋳造させて、嘉川八幡宮に寄進したものとわかる。久芳賢直は北条時政の子孫で、芸州久芳村を領して久芳氏を称し、大内氏に仕えていたが大内氏滅亡後は毛利元就に仕え、賀川地方(山口市嘉川)の領主となった。安尾春種は、長州府中(下関市長府町)の南金屋の鋳物師である。安尾氏は、その系図によると鎌倉時代から府中で鋳物師を世襲し近世に至っている。
萬福寺は嘉川八幡宮の社坊であったが、明治の神仏分離に際し、この梵鐘は嘉川八幡宮から萬福寺に移された。
規模
総高98.8cm、口径61.0cmで、上・中・下帯、草の間とも無文、乳は4段4列に配し4区合計64個。
制作者等
久芳賢直が長門府中の鋳工安尾春種に鋳造させた
製作年/建造年
天正4年(1576)
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>