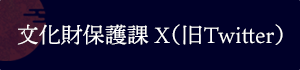本文
木造釈迦如来坐像及び両脇侍像
もくぞうしゃかにょらいざぞう および りょうわきじぞう

文化財指定等状況
市指定
指定区分
有形文化財
指定年月日
令和5年1月11日
種別
有形文化財(美術工芸品)
美術工芸品の分類
彫刻
時代(大分類)
中世
時代(小分類)
室町
地域
陶
所在地
山口市陶3907番地 正護寺
概要
説明
正護寺は、臨済宗東福寺派の寺院であり、1356年から1361年に大内氏の重臣である陶弘政を開基として創建されたと伝えられる。
3躯のうち、釈迦如来坐像の底部に「仏師法印 院什(いんじゅう)作」の陰刻 があることから、南北朝時代に活躍した院派(※1)仏師である院什の制作であることがわかる。院什の作例は3例知られており、いずれも周防国に縁のあるものであることから、大内氏が京文化を取り入れていたことと関係していると思われる。
両脇侍像も同じく院什の制作と思われ、院什の活動時期からみて、正護寺の創建時期と同じ1356年から1361年の間に制作されたと考えられる。
※1 平安時代から南北朝時代にかけて活躍した仏師の一派
3躯のうち、釈迦如来坐像の底部に「仏師法印 院什(いんじゅう)作」の陰刻 があることから、南北朝時代に活躍した院派(※1)仏師である院什の制作であることがわかる。院什の作例は3例知られており、いずれも周防国に縁のあるものであることから、大内氏が京文化を取り入れていたことと関係していると思われる。
両脇侍像も同じく院什の制作と思われ、院什の活動時期からみて、正護寺の創建時期と同じ1356年から1361年の間に制作されたと考えられる。
※1 平安時代から南北朝時代にかけて活躍した仏師の一派

制作者等
院什
関連文化財群
今に息づく大内氏の歴史文化
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>