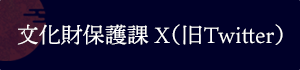本文
雲谷庵跡
うんこくあんあと

文化財指定等状況
市指定
指定区分
史跡
指定年月日
昭和57年11月27日
種別
史跡
時代(大分類)
近代
時代(小分類)
明治
地域
大殿
所在地
山口市天花一丁目12番10号
概要
説明
雲谷庵跡は、画聖雪舟の旧居跡で天花七尾山の南麓にある。雪舟は、応永27年(1420)備中赤浜に生まれ、12歳の頃生家に近い宝福寺に入って僧になったと伝えられている。その後、京都の相国寺に入り、禅とともに画技を学んだ。40歳前後に山口に来住し、寛正5年(1464)45歳の頃には、この地にあった雲谷庵に住んでいたといわれる。応永元年(1467)遣明船で中国に渡り、四明天童山で禅堂首座に列せられ、また彩色や破墨の画法を学び帰国した。帰国後も、雪舟は雲谷庵に定住し作画活動と弟子の養成に努めたが、永正3年(1506)87歳のとき山口で没したといわれている。雪舟の死後、雲谷庵には弟子の周徳、次いで3世等薩がその画統をついだが、大内氏の滅亡とともに庵はいつしか荒廃してしまった。
毛利輝元は、雪舟の画脈が絶えることを惜しみ、肥前の原治兵衛を召し出し、雲谷庵の地を与え、ここに居住させた。原は雲谷を姓とし、名を等顔と改め雪舟の画脈4世を称し、その子孫は代々毛利氏に仕えた。
明治の廃藩後、雲谷庵は無くなりその跡も忘れられるようになったので、有志等が図り、明治17年に古い社寺等の古材により庵を復興した。昭和57年に発掘調査が行われ、青磁片や瓦質土器片が見つかり、室町時代の遺構が存在する可能性が強まった。
毛利輝元は、雪舟の画脈が絶えることを惜しみ、肥前の原治兵衛を召し出し、雲谷庵の地を与え、ここに居住させた。原は雲谷を姓とし、名を等顔と改め雪舟の画脈4世を称し、その子孫は代々毛利氏に仕えた。
明治の廃藩後、雲谷庵は無くなりその跡も忘れられるようになったので、有志等が図り、明治17年に古い社寺等の古材により庵を復興した。昭和57年に発掘調査が行われ、青磁片や瓦質土器片が見つかり、室町時代の遺構が存在する可能性が強まった。
関連文化財群
今に息づく大内氏の歴史文化
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>