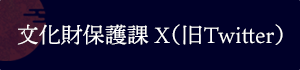本文
中河内注連縄打ち
なかがわちしめなわうち

文化財指定等状況
市指定
指定区分
無形民俗文化財
指定年月日
昭和49年10月30日
種別
無形民俗文化財
時代(大分類)
近世
時代(小分類)
江戸
地域
阿東(生雲)
所在地
山口市阿東生雲西分
概要
説明
生雲八幡宮の注連縄打ちは、毎年秋祭りの前に中河内地域の行事として世帯主総出の一日がかりで行われる。そして謹製された注連縄は八幡宮に奉納され、鳥居、拝殿などにかけられる。
享保17年(1732)9月、大鳥居が篤志家によって建立されたが、当時は総氏子集落交替の奉仕作業として注連縄打ちが行われていた。その後、天明8年(1788)8月、中河内集落一帯に疫病が流行した。集落の老若男女総員が八幡宮に参詣して平癒を祈願したところ、霊験あって疫病も漸次治ってきた。そこで、集落民集って話し合い、神慮に報いるため、注連縄打ちを申し出、以来今日まで休むことなく中河内集落の専属行事として続けられている。
享保17年(1732)9月、大鳥居が篤志家によって建立されたが、当時は総氏子集落交替の奉仕作業として注連縄打ちが行われていた。その後、天明8年(1788)8月、中河内集落一帯に疫病が流行した。集落の老若男女総員が八幡宮に参詣して平癒を祈願したところ、霊験あって疫病も漸次治ってきた。そこで、集落民集って話し合い、神慮に報いるため、注連縄打ちを申し出、以来今日まで休むことなく中河内集落の専属行事として続けられている。
関連文化財群
安穏な生活への願いと祈り